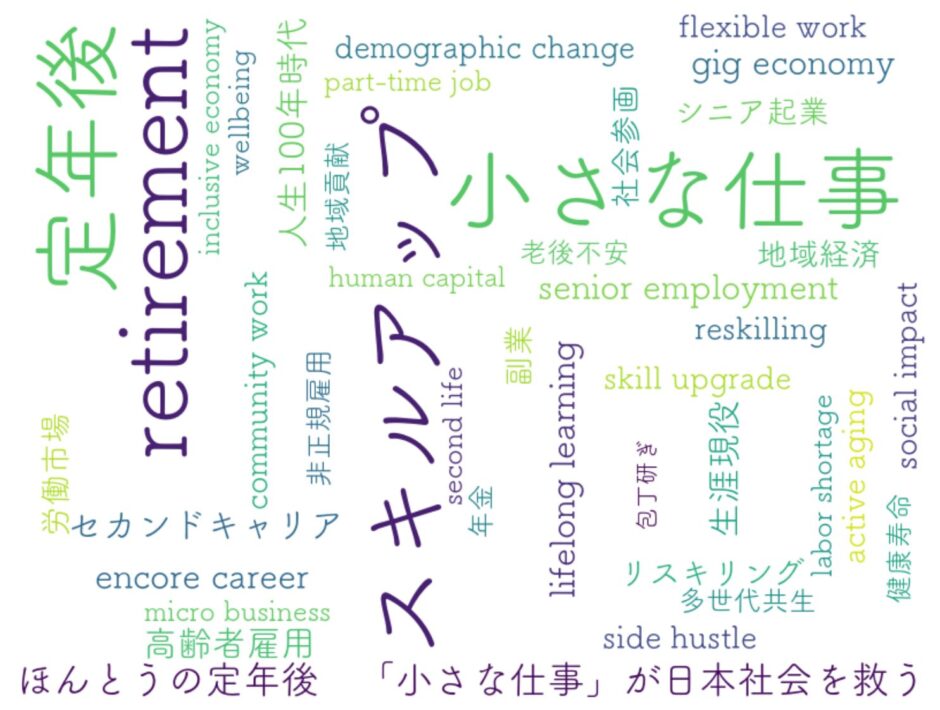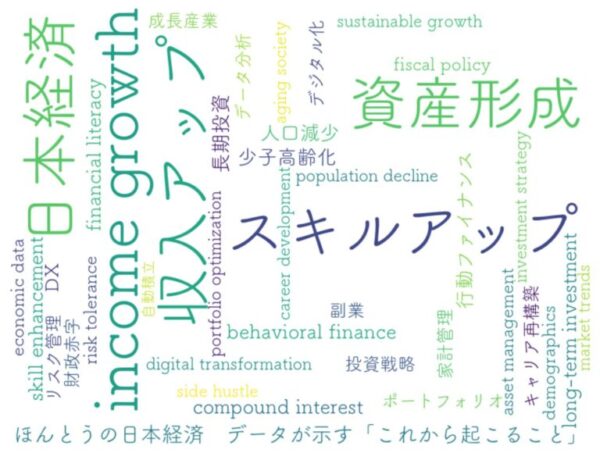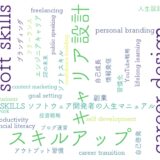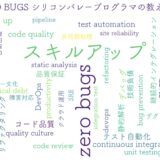この記事は最近リライトされました(2025/04/2更新)
本記事で取り上げる書籍は『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』です。
- 書名:ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う
- 著者:坂本 貴志
- 出版社:講談社(講談社現代新書2671)
- 出版年:2022年8月18日
- ISBN:978‑4065286050
年を迎えたあと、私たちの働き方はどう変わるのでしょうか。
年金だけでは生活が成り立たない、でもフルタイムでバリバリ働くのも体力的に厳しい──
そんな現実に直面したとき、「もう自分にできることはないのでは」と感じてしまう人は少なくありません。
特にこれからの日本社会では、定年後も何らかの形で働き続けることが当たり前になります。
しかし、そこに必要なのは若いころと同じ「大きな仕事」ではありません。
小さな仕事──負荷を抑えつつも、確かな役割を持った働き方が、これからの時代のキーワードになります。
本書『ほんとうの定年後』は、「定年後の仕事とは何か?」「どんな準備をすればよいか?」を、豊富なデータと実例をもとに具体的に提示してくれる一冊です。
ただ生き延びるためではなく、自分らしく社会とつながり、スキルアップと収入アップの両方を実現するために──
いまこのタイミングで、未来を見据えた働き方を考えてみませんか。
本書『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』では、定年後の働き方について、次のような重要なポイントが語られています。
本書が示すデータによれば、多くの人は定年後、年収300万円以下の「小さな仕事」へとシフトしていきます。
正社員として再雇用されるケースは少なく、非正規・フリーランスが主流。
しかし、これは決して「敗北」ではありません。
むしろ、生活スタイルに合わせた柔軟な働き方への転換と捉えるべきだと説かれます。
企業が高齢人材に求めるものは、若いころのような即戦力やトップパフォーマンスではありません。
必要とされるのは、職場を円滑に回すサポート力や、現場で周囲と調和しながら働ける柔軟力です。
新たな環境で自然体で働くためのスキルアップがカギになります。
一見、個人単位ではささやかに思える「小さな仕事」も、社会全体で積み重なれば、巨大な支えとなります。
労働力不足に悩む日本社会にとって、定年後世代の活躍は不可欠。
自分の「小さな役割」が、収入アップだけでなく、社会のサステナビリティにもつながる──
そんな誇りと意義が示されています。
定年後も生き生きと働き続けるためには、「どんなに小さな仕事でも社会に役立っている」というマインドセットが重要です。
本書では、さまざまな実例を通して、働くことそのものが人生を豊かにする力を持つことを伝えています。
本書を読んで、最も強く印象に残ったのは、「肩書きや地位にこだわらず、ただ社会の一員として役割を持つことの尊さ」です。
これまでのキャリアでは、役職や年収、影響力といった「大きな成果」が求められてきました。
しかし、定年後に必要なのは存在することそのものの価値だと本書は語ります。
たとえば、学校の用務員、地域の清掃活動、スーパーの品出しなど──
一見すると目立たない仕事でも、地域や社会を支えるために欠かせない存在になれるのです。
SEというキャリアを持つ私自身も、「プログラマー」「システムエンジニア」というラベルに縛られていたことに気づかされました。
大切なのは肩書きではなく、スキルアップを続けながら、自分らしい役割を果たすことなのだと。
意外だったのは、小さな仕事であっても、組み合わせ次第では収入アップにつながる可能性があるという点です。
本書では、週2回のパート勤務+地域のサポート業務+趣味を活かした副業といった組み合わせ事例が紹介されていました。
これにより、生活費を十分にカバーできるだけでなく、心身のリズムも保ち、自己肯定感も高まるといいます。
副業・複業が当たり前になった今、小さな仕事を積み上げるスキルは、若い世代にとっても必須の時代が来ています。
さらに心を打たれたのは、多くの高齢ワーカーが口にしていた「誰かの役に立っている実感が幸せだ」という言葉でした。
これは単なる美談ではありません。
人は社会とのつながりを失うと、心身ともに急激に衰えてしまう──
逆に、小さくても社会貢献できている実感があると、生きるエネルギーがみなぎるのです。
この意識転換こそが、定年後を幸福に生きるために不可欠な「スキルアップ」なのだと感じました。
本書『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』は、次のような方に特におすすめです。
- 退職後の生活が漠然と不安
- 年金だけでは生活が成り立つか心配
- 体力的には無理ができないが、まだ働き続けたい
こんな思いを抱える方にとって、本書は未来をポジティブに描くための「道しるべ」になります。
小さな仕事にも意義と価値があることを、実感できるでしょう。
- 今の会社に定年までいるべきか迷っている
- 退職後も何かしら社会と関わりたい
- 収入を確保しつつ、負担の少ない働き方を模索中
この世代にとって、本書は「スキルアップ」と「収入アップ」の両立を考える絶好の材料になります。
特に、自分の役割を再定義するきっかけが得られる点が魅力です。
- これからの時代、働き方はどう変わるのか知りたい
- 副業・複業を組み合わせる生き方に興味がある
若い読者にも、「仕事の規模」ではなく「仕事の意味」でキャリアを考える視点を提供してくれます。
人生の長期戦略として、「小さな仕事を積み重ねる力」がどれだけ重要かを理解できるでしょう。
- 会社一本では不安だから副収入を得たい
- 自分のスキルを小さな仕事に活かしたい
小さな仕事=副業という捉え方もできるため、今まさに副業解禁時代を生きる人にもピッタリです。
収入アップを現実にするヒントが随所に散りばめられています。
定年後、社会とのつながりを保ちながら働き続けること。
それは、これからの時代において「特別な選択」ではなく、自然な生き方になっていきます。
本書『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』は、そんな未来を明るく、前向きに描き出してくれる一冊でした。
定年後の働き方を考えるうえで、最新の就労状況データを把握しておくことは非常に重要です。高齢者の雇用状況や働き方の実態について、より詳しく知りたい方は、厚生労働省が公表している最新レポートもあわせてご覧ください。
👉 厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」(2024年度版)はこちら
定年後の働き方やキャリアシフトについて、さらに視野を広げたい方は、関連記事をまとめたこちらの一覧ページもぜひご覧ください。
👉 ライフシフト・働き方カテゴリーの記事一覧はこちら
単なる生計手段ではない、「役に立っている」という実感を得るための仕事。
肩書きや年収の大小にとらわれず、小さな役割を積み重ねることで、人生後半を豊かに彩ることができる──
そんな可能性を力強く示してくれます。
本書を読み終えた今、私は心から思います。
スキルアップとは、派手なキャリアアップだけを指すのではありません。
「変化する社会に柔軟に適応し、自分なりの役割を見つけていく力」。
それこそが、真のスキルアップなのだと。
そして、収入アップとは、高額年収を目指すだけでなく、生活を支え、自立し続けるための確かな道を築くことでもあるのだと。
この本は、「定年後どうなるのだろう」と不安を抱えるすべての人に、未来への小さな希望を与えてくれます。
これからの働き方、これからの生き方を考える上で、間違いなく「入門書」であり、そして「保存版」に値する一冊です。
迷っている方へ、最後に一言。
定年後の未来は、自分で設計できる。
そのために、今できる小さな一歩を踏み出してみませんか。
人生の後半戦を、自分らしく、しなやかに生きるために──
小さな仕事の積み重ねが、あなたの未来を大きく変えるかもしれません。
この一冊は、そんな希望の地図になります。
いま、読むべき一冊です。
class Career:
def __init__(self):
self.phase = "freeter"
self.skills = []
self.income = 0
self.risk = "high"
self.dream = "small_work_life"
def start_small_work(self):
if self.phase == "freeter":
self.phase = "small_worker"
self.income += 1
print("小さな仕事に挑戦。社会とゆるやかにつながる第一歩を踏み出した。")
def re_skill(self):
self.skills += ["flexibility", "support_skill", "community_involvement"]
print("柔軟性と地域貢献力を育みながら、スキルアップ中。")
def design_life(self):
print("人生後半設計プロジェクト開始。小さな仕事を積み重ねながら、未来をつくる旅へ。")
def next_step(self):
if self.income > 0:
print("小さな収入を積み上げ、自分らしい生き方を実現していく。")
try:
me = Career()
me.start_small_work()
me.re_skill()
me.design_life()
me.next_step()
except Exception as e:
print("今日はリスタート準備日。心を整え、次の一歩を待とう。")
finally:
print("🖖 Live long and learn.")<あわせて読みたい>
小さな仕事を通じて定年後も社会と関わり続ける働き方は、人生後半を豊かにする大切な選択肢です。しかし、私たちがこれから直面するのは、働き方だけでなく、経済環境そのものが大きく変動する未来です。
少子高齢化、労働人口減少、年金制度の見直し──こうした社会の構造変化は、個々人の生活基盤にも直結します。定年後の働き方を考えるうえでも、「日本経済が今後どうなるのか」「個人としてどのように資産を守り、生活を安定させるか」という視点は欠かせません。
未来を見据えた準備を始めるために、データに基づいて日本経済の現状とこれからを読み解き、資産防衛のヒントを探ることは非常に重要です。
定年後も安心して暮らし続けるために、そして小さな仕事を積み上げながら未来への不安を減らすために──あわせてこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。