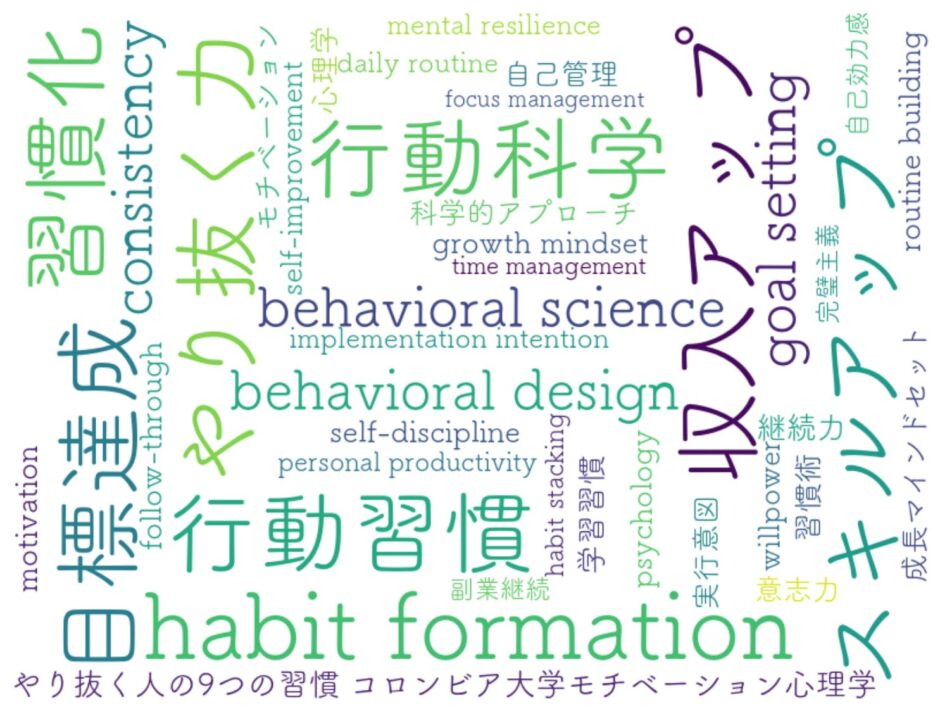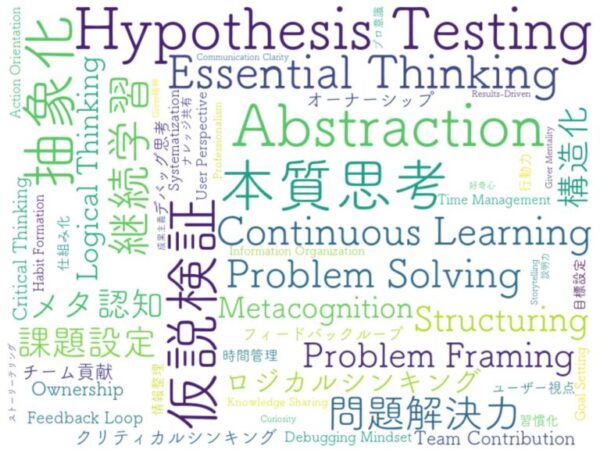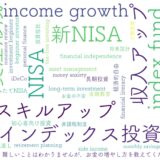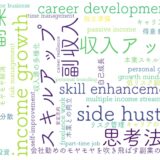本書『やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学モチベーション心理学』を読み終えたとき、多くの読者は「これなら続けられそう」という静かな確信を得るはずです。
やる気に頼らず、習慣と心理学の力で目標に向かって行動できる――そんな実感が、読み進めるほどに生まれていきます。
著者ハイディ・グラント・ハルバーソン氏が紹介する9つの習慣は、どれも科学的根拠に基づいた「再現可能な方法」です。
たとえば、「目標を具体的に書く」「計画に“もし〜なら”の条件をつける」「進捗を記録する」といった、実践しやすい行動ばかり。
それらを日々の生活に少しずつ取り入れていけば、誰でも「やり抜ける人」に変わっていけると感じさせてくれます。
本書を通じて得られる最大の変化は、「意志の力」ではなく「仕組みの力」で行動を継続できるようになることです。
これにより、学習や仕事、スキルアップ、副業、資産形成といった中長期的な目標に対しても、無理なく継続できる自分を作っていけます。
つまり、やる気の波に振り回される生活から抜け出し、科学的なモチベーション設計に基づいた“やり抜く習慣”を身につけることができる――これこそが本書の読後にもたらされる最大の価値なのです。
- 書 名:やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学モチベーション心理学
- 著 者:ハイディ・グラント・ハルバーソン
- 訳 者:林田レジリ浩文
- 出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 出版年:2017年6月
- SBN:978-4-7993-2113-3
- ASIN:B0732RRCWX
勉強でも仕事でも、「最初はやる気に満ちていたのに、続かない」「途中で挫折してしまった」という経験は誰にでもあるはずです。
タスク管理アプリを入れてみたけれど三日坊主。
自己啓発本を読んでモチベーションが上がったのに、結局元通り。
そんな繰り返しに、がっかりしたことはありませんか?
「自分には意志力が足りないのではないか」「続かないのは性格のせいかもしれない」――そう考えて、自信を失ってしまう人は少なくありません。
特にスキルアップや副業、収入アップを目指して長期的な努力が求められる場面では、「やり抜く力」が成果を左右するにもかかわらず、それを“気合い”でどうにかしようとして失敗してしまいがちです。
本書『やり抜く人の9つの習慣』は、そうした悩みを科学的に解決してくれる一冊です。
本書の立脚点は、「人は意志の強さではなく、環境や行動設計の工夫によって変われる」という心理学の成果です。
つまり、才能や性格ではなく、やり方を変えることで誰でも“やり抜く人”になれるのです。
さらに驚くべきは、そのやり方が「特別な方法」ではなく、誰でもすぐに実行できる具体的な行動習慣だという点です。
本書で紹介される9つの習慣は、日々のタスク管理、学習、仕事、投資、健康管理などあらゆる分野に応用可能。
「続けることができる自分」を作るために、今すぐ取り入れたくなる知恵が詰まっています。
その理由は、抽象的な目標(例:「健康になる」「英語を勉強する」)では、脳が「何を・いつ・どうすればよいのか」を判断できず、先延ばしが起こりやすくなるからです。
本書では「目標は“行動可能な単位”まで分解せよ」と繰り返し説かれており、たとえば「週3回、30分ずつウォーキングをする」といったように、具体的で測定可能な行動に落とし込むことが、継続の鍵になると説明されています。
この手法は、仕事・学習・副業・投資などあらゆる分野で応用可能です。私たちは「ゴール設定」を誤ると、自分を責めたり諦めたりしやすくなる──そのリスクを回避するためにも、具体性は欠かせません。
その理由は、人の行動はやる気によって左右されるよりも、「環境」と「事前の決定」に大きく依存しているからです。
本書では、やる気の波に振り回されないために「実行意図(implementation intention)」を使うことが推奨されています。これは、あらかじめ「いつ・どこで・何をやるか」を決めておくことで、脳内の抵抗感を軽減するテクニックです。
たとえば「朝8時に、リビングのテーブルで30分読書する」というレベルで事前に設定しておけば、モチベーションに頼らず自動的に行動できるようになります。スキルアップや収入アップのための行動を継続させたい人にとって、最重要の仕組みといえるでしょう。
その理由は、人は「やったことを実感できたとき」に満足感を得られ、次の行動への意欲が高まるという心理的傾向があるからです。
本書では、日記やアプリ、チェックリストなどを活用して、日々の進捗を記録することを強く勧めています。
特に「記録=ご褒美」のような認知が定着すると、行動は苦痛から快感へと変わっていきます。
この習慣は、タスク管理・学習・筋トレ・副業の作業など、どんな目標にも応用可能です。自分の成長を“見える化”することで、継続が苦手な人でも自然と続けやすくなる点が、極めて実用的です。
その理由は、「成果が出ないと意味がない」と考える達成型の目標に比べて、「努力やプロセスを評価する」成長型の目標は、多少の失敗やスランプがあっても継続しやすくなるからです。
本書では、進捗が芳しくないときこそ「自分が今、どのように成長しているか」に意識を向ける重要性が語られています。
たとえば「月収を10万円増やす」ではなく「週に2本のブログ記事を書く習慣を定着させる」といった目標設定にすると、成果が見えづらい初期段階でも前向きに取り組みやすくなります。収入アップを目指す人こそ、“成長を目的にする”マインドセットの重要性を本書から学ぶべきです。
その理由は、具体的な“条件反射的行動”を事前に準備しておくことで、迷いや中断を防ぎ、スムーズに行動に移れるからです。
この手法は「if-thenプランニング」と呼ばれ、たとえば「もし残業があったら、帰宅後に15分だけストレッチをする」といった形で活用されます。
本書でも、「人は行動の自動化を設計することで、継続力を大きく高められる」と述べられています。特に習慣化したい新しい行動に対してこのテクニックを取り入れると、日常の雑音に流されることなく、目標へのルートを自動でたどれるようになるのです。
やる気は行動の“前提”ではなく、“行動のあと”に生まれる。
これまで「やる気が出たら始めよう」と考えていた自分の発想が逆だったことに気づかされました。行動→やる気、という流れを前提に設計すれば、手が止まる言い訳がひとつ消えます。
毎朝5分でも机に向かう“儀式”を習慣化し、気分よりも先に行動する流れをつくります。これによりスキルアップに直結するインプット量の底上げを狙います。
習慣化や行動変容の重要性は、教育や学びの分野でも広く注目されています。特に「目標の立て方」や「継続の仕組みづくり」といった観点は、学校教育やリスキリング支援にも応用されています。
こうした教育現場での実践的な研究や知見を深めたい方は、国立教育政策研究所(NIER)の公式サイトもぜひご覧ください。
👉 国立教育政策研究所(NIER)公式サイトはこちら
習慣化や行動変容を通じて「やり抜く力」を身につけた後は、人生全体の設計にも目を向けてみませんか?
当ブログの「ライフシフト・働き方」カテゴリでは、キャリアの再構築や副業の始め方、学び直しの実践例など、人生100年時代を見据えた多様な働き方・生き方のヒントを多数ご紹介しています。
👉 「ライフシフト・働き方」の記事一覧はこちら
“いつ・どこで・どうするか”を事前に決めておく「実行意図」が行動実行率を高める。
ToDoリストや目標設定だけで満足してしまっていた自分にとって、「実行の瞬間」を仕込む発想は非常に実用的だと感じました。
副業や投資学習など、毎日30分の「定位置タスク」を決め、時間と場所のトリガーで自動化します。結果として、収入アップを支える習慣資産を構築していきます。
結果に一喜一憂せず、「昨日より少しできたこと」に注目するほうが継続しやすい。
「自分は結果が出ない」と焦る気持ちが、行動のブレーキになっていたことに気づきました。前進を実感できる視点は、自己肯定感にもつながります。
毎日の学習ログに「今日の前進」をひと言書き足します。これにより行動と成長をリンクさせ、継続しやすい学習ループを構築していきます。
完璧を目指すあまり着手が遅れるより、60点でも始めたほうが成果につながる。
「全部そろってから始めたい」「もっと勉強してから動きたい」と思う癖が、結果的に機会を逃していたことに気づかされました。
新しい習慣や行動は“仮運用”として試すクセをつけます。たとえば「とりあえず10日やってみる」ことで、心理的ハードルを減らしつつ実行力を高める構えを整えていきます。
その理由は、時間のやりくりやモチベーション維持に苦戦しがちで、「やるべきことは分かっているのに動けない」悩みを抱えているからです。
本書で紹介される9つの習慣は、行動のトリガー設計や小さな継続の積み重ねにフォーカスしており、副業継続の土台作りに最適です。
その理由は、「新しい知識を学ぶこと」はできていても、それを習慣化して成果につなげるフェーズでつまずきやすいためです。
本書は“才能や根性ではなく、仕組みで行動を支える”というアプローチを提供してくれるため、日々の継続に悩む技術者にこそマッチします。
その理由は、一度やろうとして挫折した経験がある人ほど、「今回はやり切りたい」という思いが強いからです。
モチベーションではなく“実行の設計”に基づいた本書の習慣は、再挑戦する人の背中を優しく、かつ科学的に後押ししてくれます。
その理由は、目標を高く設定しすぎたり、最短距離で達成しようとして失敗しがちな傾向を持っているからです。
本書は「成長目標」に意識を向けることで、自分を責めずに前進できるメンタル設計を教えてくれます。行動の再起動がしやすくなります。
「意志が弱いから続かない」「また途中でやめてしまうかもしれない」――そんな不安を抱えて行動できないでいる人にとって、本書『やり抜く人の9つの習慣』は、まさに救いの一冊です。
私たちはとかく「やる気」や「根性」に頼りがちですが、本書はそれらではなく、行動科学に基づく“仕組み”で自分を変える方法を教えてくれます。
しかも、その習慣は誰でも今日から始められるようなシンプルで現実的なものばかり。
だからこそ再現性が高く、応用の幅も広いのです。
読み終える頃には、「もっと早く知っておけばよかった」と感じるかもしれません。
けれど今からでも遅くありません。
小さな目標を具体的に設定し、「いつ・どこで・何をするか」を決める。
その積み重ねがやがて、スキルアップと収入アップを実現する土台となるでしょう。
「自分を変えるには何から始めたらいいのか」と悩んでいるすべての方へ──
まずはこの1冊から始めてみてください。
行動の“仕組み”を知れば、未来はもっと変えやすくなります。
やる気が続かない、習慣が身につかない、自分に甘くなってしまう──そんな悩みを、もう繰り返さないために。
本書『やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学モチベーション心理学』は、あなたの「やりたいことを最後までやり遂げる力」を、科学的にサポートしてくれます。
スキルアップを本気で目指す人にも、収入アップを目指す副業チャレンジャーにも。
行動の土台を作るための“仕組み”が、この1冊には詰まっています。
「変わる方法」が知りたいなら、まずは読むことから始めてみませんか?
下記のリンクから、今すぐチェックできます。
class HabitRebuilder:
def __init__(self):
self.status = "習慣化未達"
self.willpower = 0.4
self.triggers = []
self.success_streak = 0
def define_goal(self, goal):
self.goal = goal
print(f"目標を設定しました → {goal}")
def set_implementation_intention(self, when, where, action):
plan = f"もし{when}なら、{where}で{action}する"
self.triggers.append(plan)
print(f"実行意図を登録しました:{plan}")
def act(self):
try:
if self.triggers:
print("トリガー条件に従って自動行動を実行中...")
self.success_streak += 1
self.status = "継続中"
else:
raise ValueError("実行意図(implementation intention)が未設定です")
except Exception as e:
print(f"習慣化失敗:{e}")
self.success_streak = 0
self.status = "リセット"
finally:
print("🖖 Live long and learn.")
# 実行例
if __name__ == "__main__":
user = HabitRebuilder()
user.define_goal("毎朝30分の副業作業を継続する")
user.set_implementation_intention("朝7時", "自宅のデスク", "副業の作業を始める")
user.act()<あわせて読みたい>
「やり抜く習慣」を支えるのは、仕組みだけでなく“思考の土台”です。
行動を継続できる人は、思考も柔軟に進化させています。
習慣化に加えて、より高度なスキルアップや自己成長を目指したい方には、一流エンジニアのマインドセットに迫ったこちらの記事もあわせてご覧ください。